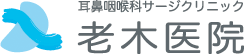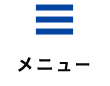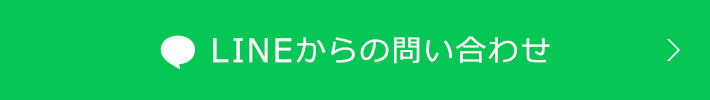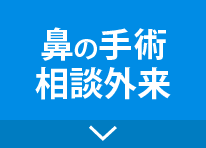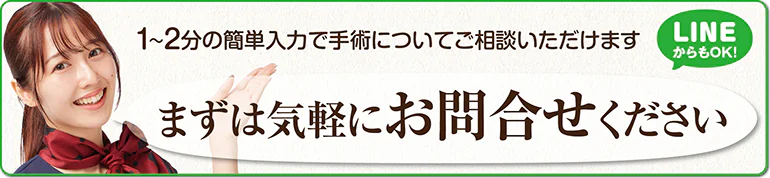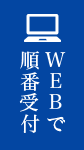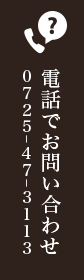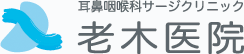耳が詰まった感じ、ふさがった感じというのは非常に不快なもので、耳閉感(じへいかん)と呼ばれるものです。その原因はいろいろありますし、病気によっては早く治療を始めないと治りにくくなる病気もありますので、早めの耳鼻科受診がおすすめです。
まずは耳が詰まった感じがする症状のセルフチェック
耳が詰まった感じ(こもる・塞がる・水が入った感じ・左耳だけ など)は、外耳・中耳・内耳・耳管と原因が複数あり、最適な“治し方”が異なります。まずは危険サインの見落としを防ぎ、受診のタイミングを判断することが近道です。
このセルフチェックでは、次の3点を簡単に判定できます。
- 今すぐ受診が必要か
- 本日〜数日以内に受診すべきか
- 自宅で先に試せる対処と、避けるべき行為
結果に応じて、検査→治療→手術相談の最短ルートをご案内します。
※本チェックは目安です。症状が急に悪化した場合は、表示結果にかかわらず早めに受診してください。
今すぐ受診が必要な症状
- 突然、片側(または両側)の聞こえが急に低下した
- 強いめまい(立てない・吐き気を伴う)や、激しい耳の痛みがある
- 38℃以上の発熱、膿のような耳だれ、症状が急速に悪化している
- 耳の後ろの強い痛み、顔の動かしにくさ(顔面まひの疑い)を伴う
1つでも当てはまる場合は至急受診してください。医師が診察し、必要に応じて治療〜手術相談まで対応します。
本日〜数日以内に受診をおすすめする症状
- 詰まった感じ・こもり感が2〜3日以上続く/何度も繰り返す
- 耳鳴りや聞こえの質の変化(遠く聞こえる・こもって聞こえる)が続いている
- 軽い痛みや発熱、耳だれが残っている
- 風邪のあと/飛行機・ダイビング後に詰まりが長引いている
耳閉感は原因の部位によって対処が変わります。早めの受診が安心です。
左耳だけ・右耳だけが詰まるときの注意点
- 片側の“詰まり”に耳鳴りや聞こえの低下を伴う場合は、急性の内耳疾患を含む可能性があります。できるだけ早期の受診をおすすめします。
- 片側の詰まりにめまい発作を反復する場合は、めまい疾患の可能性があるため専門的な検査を検討します。
- 風邪・アレルギー・気圧変化のあとに片側だけ続く場合は、耳管のトラブル(狭窄・開放)などでも起こります。数日で改善しない場合は受診の目安です。
片側症状は病変部位の手がかりになります。診察で原因と重症度を見極め、適切な対処につなげます。
自宅でできる対処(治し方)とやってはいけないこと
軽い“詰まった・こもった・塞がった感じ”は、まず自宅でできる対処を試しつつ、悪化につながる行為はしない事が大切です。症状が長引く場合は当院へご相談ください。
軽い“詰まった感じ”の対処法
嚥下・あくび・ガム咀嚼
飲み込む・あくびをする・ガムを噛むと耳管が開きやすく、こもり感の軽減が期待できます。飛行機の離着陸時にも有効です。
やさしい耳抜き(バルサルバ法)
口を閉じて鼻をつまみ、軽く息を送り込みます。強く何度も行うのは逆効果のため避け、痛みが出たら中止してください。
正しい鼻洗浄(鼻うがい)
生理食塩水をゆっくり使用します。水は蒸留水・滅菌水・沸騰後に冷ました水を用い、器具は清潔に保ちます。洗浄後はやさしく鼻をかみます。
加湿・温蒸気
室内を適度に加湿し、温かい蒸気で鼻の通りを助けます(やけどに注意してください)。
気圧変化への備え(飛行機・ダイビング前後)
離着陸の少し前から嚥下・咀嚼を意識し、必要に応じて耳用の耳栓を活用します。鼻やのどの症状が強いときは無理をしないことが大切です。
※2〜3日で改善しない、悪化する、耳鳴りやめまいを伴う場合はすぐに受診しましょう。
やってはいけないこと
耳の中に物を入れない
外耳道や鼓膜を傷つけたり、耳垢を奥へ押し込む原因になります。
強い耳抜きや反復しすぎ
高い圧で何度も行うと鼓膜や内耳を傷めるおそれがあります。耳抜きはやさしく最小限にとどめます。
鼻うがいの誤った方法
水道水をそのまま使う/器具が不衛生/勢いよく流す/飲み込む、などは感染や中耳炎のリスクを高めます。
独自判断での薬剤の長期連用
市販薬や点耳薬を漫然と使い続けるのは避け、症状が続く場合は原因に合わせた対応が必要です。
症状が強い状態でのダイビング・無理な飛行
痛みや強い詰まりがあるときは、さらなる悪化につながることがあります。
注意:激しい痛み、38℃以上の発熱、膿のような耳だれ、突然の片側の聞こえの低下、強いめまいは自宅対応の範囲を超えます。早めの受診をおすすめします。
耳が詰まった感じの原因
中耳に異常がある場合
急性中耳炎・慢性中耳炎

急性中耳炎や慢性中耳炎で中耳に膿がたまったり、鼓膜に穴が開くと、聴力がやや低下して、耳閉感が出てきます。
外傷性鼓膜穿孔
外傷性鼓膜穿孔といって、鼓膜を耳掃除で突いてしまったり、平手で耳をたたいた空気の衝撃で鼓膜が破れることもあります。
滲出性中耳炎
幼児期と高齢者に多いのは、滲出性中耳炎といって鼓膜の奥に滲出液が溜まった状態で、不快な耳閉感がよく起こります。幼児期は耳閉感を自分で表現できないことが多いので、耳を気にしてそうな仕草をした時には耳鼻科を受診していただきたいです。
耳管開放症といって、中耳と鼻咽腔をつなぐ細い管の働きが異常な場合でも耳閉感につながることがあります。
外耳に異常がある場合
外耳炎
外耳に何か異物が入ったり、外耳道が狭くなった場合には耳閉感を感じます。外耳炎で外耳の皮膚がハレて外耳道が狭くなる場合があります。
サーファーズイヤー
サーファーの方などで、長年、外耳が冷水にさらされると外耳の骨が盛り上がってきて狭くなり(骨腫)、やはり耳閉感が出てきます。これをサーファーズイヤーを呼びます。
外耳道内に水が入り、なかなか抜けない場合、耳垢がたまって完全に外耳道がふさがってしまった場合などがあります。
外耳や中耳に異常がない場合
診察上、全く問題がなくても、聴力検査をすると、聞こえが悪くなっている場合があります。主として、内耳の病気の場合で、代表的な病気は、突発性難聴、低音障害型感音難聴、メニエール病などがあります。
他に、ロック・コンサートなどで大音量の音を聞いた後に聞こえが悪くなったり、耳閉感が出る場合があります。これは内耳が大音響で障害を受けた状態で、音響外傷と言います。早めに受診していただきたい状態です。
めまいや耳鳴りなどを伴う場合と伴わない場合があります。突発性難聴の場合は早く治療を開始しないと治癒率が低下するといわれていますので、できるだけ早くに受診する必要があります。
耳が詰まった感じの治療法
急性中耳炎

比較的軽度の場合、お薬による治療が主体となります。抗生物質の内服、点耳薬などを使用します。
強い耳の痛みや発熱が続く場合、保存的治療だけでは十分な効果が期待できない場合には、鼓膜切開術による治療を行います。鼓膜のごく一部を切開し、中耳内の膿を取り除きます。
慢性中耳炎
細菌の増殖を抑えたり死滅させるために、抗菌薬(抗生物質など)を飲んだり、点耳薬を用いたりします。肉芽や真珠腫がある場合にはそれらを取り除く手術を行います。鼓膜の穴をふさぐ手術(鼓膜形成術)や、耳小骨が損傷している場合はこれを修復する手術(鼓室形成術)を行います。
外傷性鼓膜穿孔
小さなものであれば、鼓膜の穴は自然にふさがります。この場合入浴や水泳で耳に水が入らないように注意し、耳の中を乾燥で清潔に保ちます。
感染症を起こしている、または感染症が疑われる場合は、抗菌薬の経口投与や点耳薬の外用での治療を試みます。
2か月以上穴がふさがらない場合は手術が適用となります。
滲出性中耳炎
幼小児期と高齢者では治療法が違ってくることがあります。
高齢者では、治療法は確立していませんが、
外耳炎
軽い外耳道炎であれば、耳掃除をしないようにするだけでも自然に治ります。ステロイド入り軟膏や抗生物質入り軟膏を状態に応じて塗ります。
炎症や痛みが強い場合には抗生物質や痛み止めの内服薬を処方します。炎症が高度な場合には、皮膚切開で排膿する処置や抗生物質の点滴が必要な場合もあります。
サーファーズイヤー
手術によって原因となる骨腫を取り除きます。サーファーズイヤー担当医のホームページにて詳しく解説しております。
内耳の病気
内耳の病気の場合、早めに医療機関を受診しないと治療が手遅れになる場合があります。耳のつまった感じが続く場合やすぐに治っても繰り返す場合には、すぐに耳鼻科を受診しましょう。
耳が詰まった感じがしたら、お気軽にご相談ください。
耳が詰まった感じがしたら、耳鼻科の受診をお勧めします。大阪・和泉市の耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院では耳の治療を行っております。
地域密着で安心の診療体制
耳鼻咽喉科サージクリニック老木医院は、地域に住む皆さまが安心して通える耳鼻科を目指しています。小さなお子さまからご年配の方まで、幅広い世代の鼻の症状に対応。普段から気軽に相談できる「かかりつけ医」として、長く信頼いただける診療を行っています。
専門医による丁寧な診察と治療
当院では経験豊富な耳鼻咽喉科専門医が、一人ひとりの症状に合わせた治療を行います。わかりやすい説明を心がけ、不安や疑問を解消しながら治療を進めていきます。
予約・お問い合わせはこちら
耳が詰まった感じでお悩みの方は、どうぞお気軽に当院へご相談ください。
症状が軽いうちに治療を始めることで、早い改善につながります。まずは一度、ご相談ください。お仕事帰りや学校帰りにも通いやすい体制を整えています。
治療に関するご相談を希望される方はまずは下のボタンより一度お問い合わせくださいませ。
耳に関するその他の症状
以上耳が詰まった感じの原因と治療法について解説させていただきました。その他の耳に関する症状は以下のページにて解説しております。